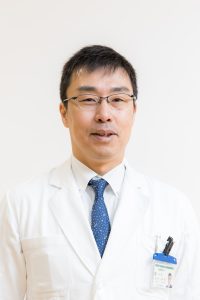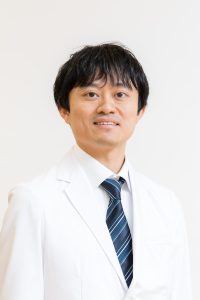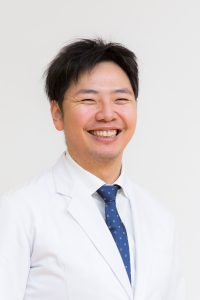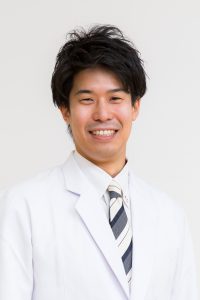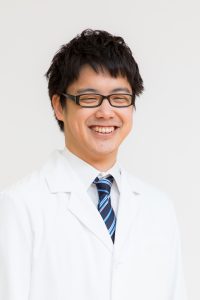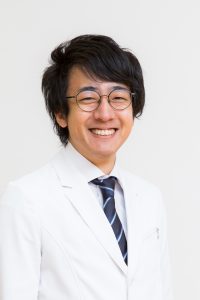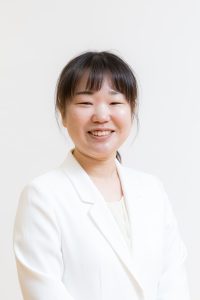心不全のトータルケア
多職種介入による集学的な治療戦略の構築と実践
近年、高齢化社会の到来とともに循環器疾患における疾病構造は大きく変化し、心不全患者は急増しております。また、心不全治療を取り巻く環境は目覚ましく発展し、多様化を認めております。北海道大学病院循環器内科心不全班では、多職種介入のもとで心不全診療に対する集学的な治療戦略の構築と実践に取り組んでおります。包括的治療プログラムを通した適切な運動療法、食事指導、疾病教育の徹底を前提とし、心不全に対する十分な至適薬物療法の検討、腫瘍循環器などを含む各種病態別の対応に加え、心臓リハビリテーション、経カテーテル的大動脈弁置換術(TAVI)、経皮的僧帽弁接合不全修復術(MitraClip®)、心臓再同期療法、植込み型除細動器、カテーテルアブレーションに代表される非薬物療法、更には左室補助人工心臓(LVAD)や心臓移植といった末期重症心不全患者に対する治療について幅広く適応を検討し、多面的かつ長期的な視野に立って適切な時期に、適切な治療を、適切な患者に行うことを目標としております。
-
#01
心不全の検査・診断
-
#02
心不全の重症度に応じた治療
多職種心不全カンファレンスの取り組み
毎週行われる重症心不全カンファレンスでは、入院・外来の心不全症例における治療方針の共有を行い、至適な心不全治療の確認を全体で行っております。初回心不全患者や一年間に数回の心不全入院を繰り返すような、心不全教育が特に重要と判断された症例においては、心不全パスカンファレンスを開催し多職種介入(病棟看護師、管理栄養士、理学療法士、薬剤師、医師)のもとでセルフケア評価尺度や心不全チェックリストを運用し、各職種における評価を共有することで心不全患者の生活の中に潜む心不全増悪要因を把握し、それに合わせた適切かつ患者・ケアギバーの価値観や思いに沿った心不全セルフケア支援を進め、再入院の予防に努めております。また、このような多職種介入の取り組みを心不全地域連携手帳(さっぽろ心不全ネットワーク監修)に反映することで、心不全治療内容を患者、ケアギバー、大学病院以外の施設と共有できるよう工夫をしております。今後もより包括的に心不全患者を支援できる体制の構築を進めてまいります。
心臓リハビリテーション
心臓リハビリテーションでは、心血管疾患患者の体力や不安・抑うつ状態を改善し、動脈硬化や心不全の病態の進行を抑制あるいは軽減し、社会復帰を実現し、再発・再入院・死亡を減らすことを目指しております。多職種チームが協調して個々の患者に対して運動療法・生活指導・カウンセリングなどを実践することで、長期にわたる多面的・包括的プログラムを行えるよう工夫をしております。近年、社会の高齢化に伴う高齢者心不全の急増やTAVI、MitraClip®実施件数の増加を反映して、当科への高齢者の入院が目立つようになってきました。高齢者は心臓だけでなく、他にもさまざまな疾患を抱えていることが多く、フレイル(虚弱)やサルコペニア(筋力低下)、認知症といった特有の問題を抱えており、入院時から心臓リハビリテーションを導入し、退院後も適切なアドバイスに基づいた運動・生活の指導を受けることができるよう配慮しております。
-
#09
心臓リハビリテーションの流れ
-
#10
当院の心臓リハビリテーション室
腫瘍循環器
がん治療と循環器内科
近年、人口の高齢化に伴い心血管疾患を合併したがん患者が増加し、がん化学療法や放射線治療による心不全を代表とする心血管合併症が、がん治療継続を困難とさせている問題に直面することがあります。また、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬などの新たながん化学療法による心血管合併症の出現や、がんサバイバーにおける長期的な心血管リスクの問題点もあります。先進的な医療の開発と提供の役割を担う北海道大学病院では、近年特にがん診療と循環器診療の新たな協力体制が求められております。心不全班では、循環器内科の立場から「がんを患った患者の心臓を守る」ことを目的として、がん患者の治療中に起こる心血管合併症の診療や、循環器疾患を抱えた患者さんのがん治療を円滑におこなうサポートが行えるよう、チームで取り組んでおります。
心不全患者におけるアドバンス・ケア・プランニング
近年、心不全が症候性となったより早期の段階からアドバンス・ケア・プラニング(advance care planning; ACP)を行うことの重要性が指摘されております。当科科長 安斉俊久教授が班長としてまとめられた「2021年改訂版 循環器疾患における緩和ケアについての提言」が日本循環器学会より発表され、本邦において心不全緩和の概念が急速に普及し始めております。我々のチームにおいても安斉教授のご指導のもと、疾患の治療法がなくなった段階で切り替わって提供される緩和ケアではなく、より軽症の段階から終末期を含めた状態変化に備えるためのACPを継続し、患者・ケアギバーと病状を共有しながら、患者の人生観を尊重した積極的治療を行うことができるよう努力しております。意思決定支援や全人的苦痛の評価をはじめとした基本的な心不全緩和ケアの関りは病棟スタッフを中心とした心不全多職種チームが担当しますが、複雑な意思決定支援、難治性苦痛に関しては心不全緩和ケアチームと協働し診療に取り組んでおります。心不全緩和ケアチームは循環器内科医師、精神科医師、緩和ケア科医師、病棟看護師、薬剤師、栄養管理士、理学療法士、臨床心理士、レシピエント移植コーディネーター、メディカルソーシャルワーカーといった多職種から構成されます。毎週のカンファレンスにおいて多職種間で情報共有を行うだけでなく、患者報告型アウトカム評価尺度の一つであるIPOSやNAT:PD-HFといった評価ツールを運用することで、患者・ケアギバーの抱える潜在的な問題点を抽出し、ニーズの把握を行い、全人的な苦痛に対して包括的に介入することを目指しております。
-
#06
心不全治療と緩和ケアの関係
-
#07
心不全緩和ケアチームの概念
重症心不全診療
道内基幹病院との連携
北海道大学病院は北海道で唯一の心臓移植実施施設として、道内各地より重症心不全症例の紹介があります。状況に応じて迅速に紹介施設に往診のうえ、治療方針のコンサルテーションに対応しております。また、現在道内10施設の基幹病院において、医用画像共有プログラムであるCaseline®の導入が完了しております。本システムは北海道大学病院循環器内科の専門診療チーム(心不全班・心臓カテーテル班・心エコー班・不整脈班)と道内各地の基幹病院の医師をつなぎ、心電図やエコーといった医用画像・映像を共有しながら音声通話で遠隔診断および診療をサポートするものです。これにより、患者の病態や治療方針に関して大学病院と緊密に連携を取りながら、必要に応じた迅速な転院および治療開始が可能となりました。
左室補助人工心臓(LVAD)/心臓移植
LVAD・心臓移植の適応と判断され得る症例で、患者が希望された場合には、当院に搬送の上、速やかにかつ安全に次の治療へ移行できるよう心がけております。転院後は病状評価・集学的治療と併行して、多職種介入による意思決定支援を行い、精神的・身体的サポートを継続できるよう取り組んでおります。VAD装着中及び移植後管理における様々な問題に関しては、毎週開催されるVAD・移植カンファレンスにて多職種介入(循環器内科医師・循環器外科医師・ICU医師・精神科医師・臨床心理士・病棟看護師・臨床工学士・理学療法士・薬剤師・管理栄養士)のもと、安全性を最優先とした治療戦略や心理的・社会的問題に関して議論しております。
北海道大学病院は2023年7月より心臓移植を前提としないLVAD治療であるdestination therapy(DT)の実施施設と認定されました。これまでの重症心不全治療および心不全緩和ケアの経験を最大限活かしながら、今後も治療の普及に努め、安全性とQOLを重視した支援を継続してまいります。
-
#05
HeartMate3 (提供:ニプロ株式会社)